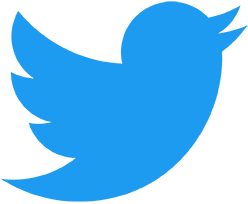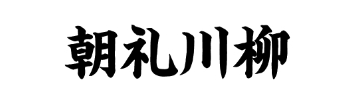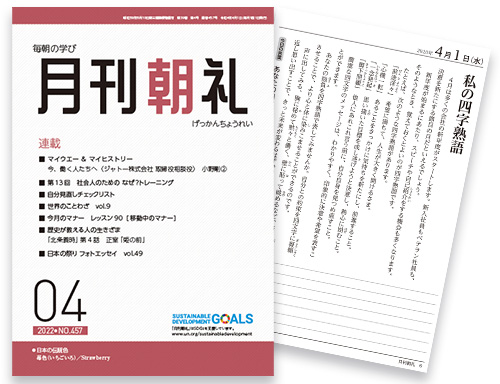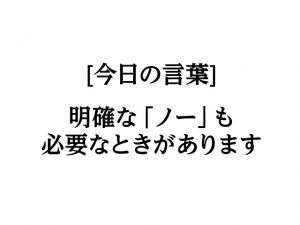
おはようございます。
「来週の会合には参加できますか?」という質問に、「仕事があるかもしれないので、行けたら行きます」と答える人がいます。
社会人の事情として、即決できないこともあるでしょう。しかし、はっきりと断ることは、相手のメリットにもなるのです。早めに断ることで、主催者は他の人に声を掛けることもできますし、準備を進めることも可能です。
曖昧な返事より、「ノー」という返事を待っている場合さえあるのです。
社内では、
「私もよく、お誘いがあったときに『行けたら行きます』という返事をしています。相手のことを考えない自分本位な言葉であると、あらためて反省しました。曖昧な返事をしていたのは、『はっきり断ると角が立つ』と考えていたからだと思います。これからは、相手のためにも、明確な答え方をしていきたいです」
「私は会合の幹事を任されることが多いのですが、『行けたら行きます』という答えは一番困ります。そのため自分が返事をするときは、幹事が困らないよう明確に答えるようにしています。即決できない場合は、『来週にはスケジュールが確定するので、その際にお返事いたします』など、はっきり期限を決めれば相手の不安も減るはずです」
「時には相手のために『ノー』を言うことが大切なのは確かです。しかし、せっかくのお誘いを『行けません』とだけ断るのも失礼になると思います。たとえば、『今回は出席できず申し訳ございませんが、次回は必ず出席します』など、前向きな印象を残すようにしたいです。さらに、『残念ながら私は行けませんが、代わりの者を行かせます』など、代替案を用意できれば、なおよいと思います。『ノー』であっても、できるだけ『イエス』に近い肯定的な答えができるよう、普段から努力しています」
という意見が出ました。
日本の文化として、「イエス」「ノー」をはっきりさせないことがよくあります。もちろん、それも相手を傷つけないための心遣いには違いありません。しかし、「角が立たないように」という曖昧さが、相手を困らせることも多いのです。
南アフリカ大統領だったネルソン・マンデラさんも、「ノー」とはっきり言うことの重要性を説いています。「ノーには意味がある。曖昧に返事をするよりは、はるかに相手のためになる」としています。
保留してばかりいる人は、自分の都合ばかりを重視していないでしょうか。相手のためには、ときには決断力を持って、明確に返事をすることも大切です。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」