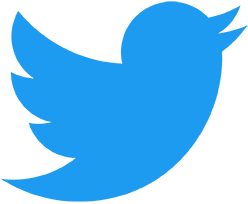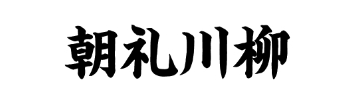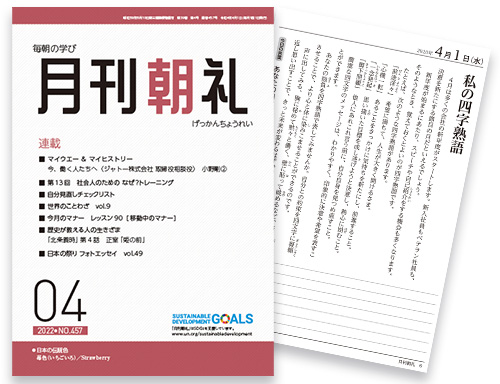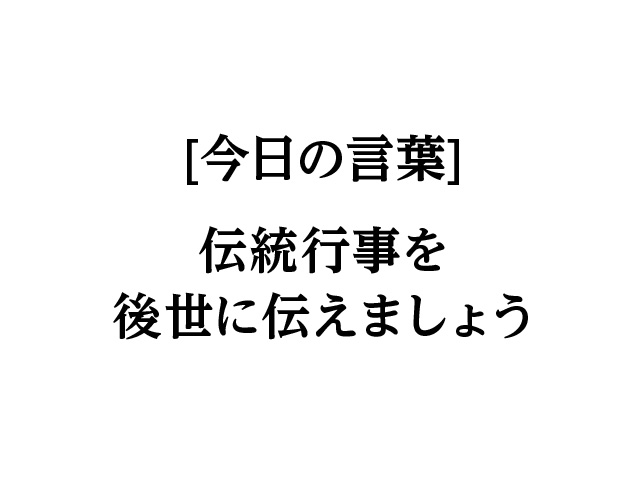
おはようございます。
本日は、神仏に感謝し、無病息災などを祈る「鏡開きの日」です。鏡開きは、供えて硬くなった鏡餅を、金づちなどでたたいて「開く」日本の年中行事です。鏡餅は、歳神様が宿る場所であるため、神様とも縁を切らないように「割る」や「砕く」とは言わず、末広がりを意味する「開く」という縁起のよい表現を使うのです。鏡餅を食べることを「歯固め」といい、固いものを食べて歯を丈夫にし、歳神様に長寿を願うことからだといわれています。
社内では、
「小学生時代、田舎で暮らしていたときは、冬休みに宿題はありませんでした。なぜなら、子どもたちも正月の準備で忙しいからです。裏の竹やぶから竹を切って門松を作ったり、祖父母と一緒にしめ縄を編んだりしました。今は子どもに教えられていないので、来年は子どもと一緒に挑戦しようと思います」
「核家族化や年中無休店舗が増え、日本の伝統行事が時代とともに様変わりしてきています。しかし、日本古来の行事にはそれぞれ意味があるため、それを学ぶことは日本人にとって意義のあることです。家庭のなかで代々引き継いでいきたいです」
「今朝、テレビでおいしい鏡餅の食べ方の特集をしていました。会社で本文を読み、今日が鏡開きの日であることを知って、納得しました。これからもさまざまな日本の行事について知りたいです」
という意見が出ました。
鏡開きは、歳神様を敬い、信じて祈る日本人の敬虔な信仰心を感じる行事です。今一度、伝統行事の意味を考え直し、家庭を通して、その心を若い世代に伝えていきましょう。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」