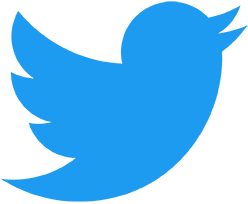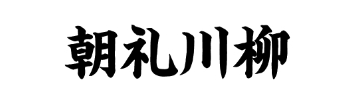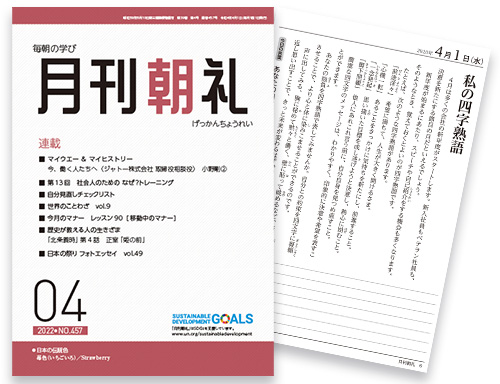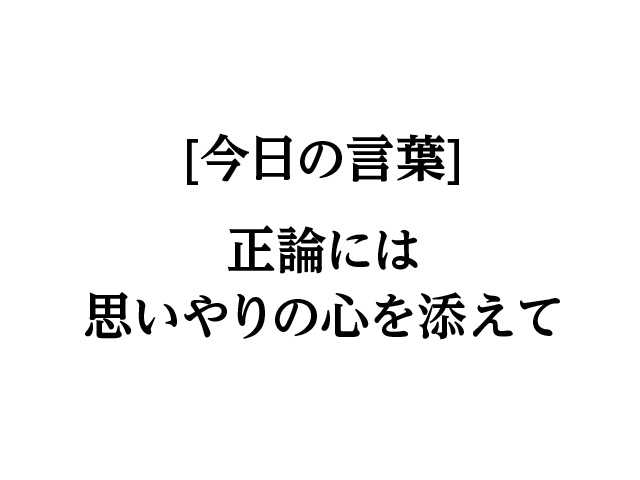
おはようございます。
上司は部下に、また、親は子どもに対して、教育のために正論を言うことがあります。
怠けていると思えば「もっと真面目にしろ」、挫折して落ち込んでいるときは「逃げるな、乗り越えろ」、また、人間関係に悩んでいるときには「みんな仲よくしろ」などと言います。
しかし、正論という名のもとには、次のような問題が潜んでいます。
1 頭でわかっていても実際にできないとき、冷たく突き放すことになる
2 理屈が正しいために反発できず、かえって自信を失わせることになる
3 できるはずだという前提に立つため、押しつけがましくなる時と場合によっては、正論を言われても、言葉通りにできないこともあるでしょう。そのことを心にとどめて、指導する必要があります。
社内では、
「私は、子どもに正論を言ってしまうところがあるため、今日の話は、身につまされました。子どもは、言われていることが正しいとわかっているために反論できず、自信を失って相談してこなくなっていると感じるので、子どもの気持ちや立場をよく確認し、理解したうえで、逃げ場のある状況をつくってあげなければいけないと考え直しました」
「正論を言う場合、『こちらが正しくて、相手が間違っている』と思い込んでいるため、どうしても相手を責める言い方をしてしまいがちです。そうすると、相手も反発してきます。しかし、思いやりの心を添えて説明すると、相手も気持ちよく受け止めてくれます。正論を伝える場合は、相手に敬意を持って接することが大切です。そのためには、時に自分の経験談を語ったり、いくつかの手段を提示したりするのも有効です」
「後輩などから相談を受けたときは、こちらの言い分だけを押しつけるのではなく、相手の状況を考慮して、その状況にふさわしいアドバイスをするようにしています。そうすると、少し困難なことでもやってみようと思ってくれるようになります。相手のことも自分のこととして捉えましょう」
という意見が出ました。
よかれと思って言った正論であっても、結果的に人を傷つける場合があります。正論を言う場合は、相手の心と向き合いながら、「相手を育てるための言葉になっているだろうか」と、自分の言動を客観視し、思いやりの心を添えることが重要です。そうすれば、言われた側も納得することができ、良好な関係を築くことができるはずです。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」