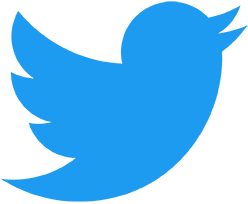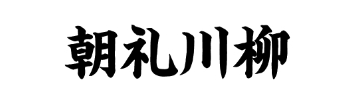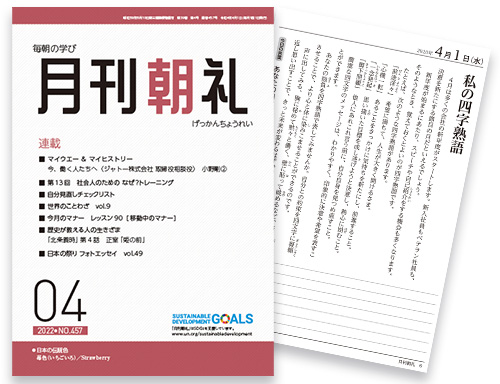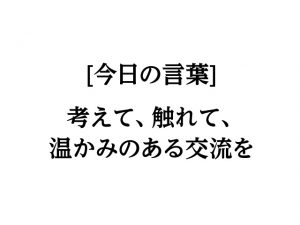
おはようございます。
ボードゲームや野球盤などの「アナログゲーム」を活用する試みが、兵庫県西宮市の小学校で始まっています。テレビゲームやスマホゲームに親しむ小学生に、人間関係を学ぶ機会を与えることが狙いです。
一人でテレビやスマホのゲームに熱中する子どもが多い近頃、学年やクラスを超えた仲間とアナログゲームを囲む時間は、何物にも替えがたいものです。会話が自然に生まれるため、コミュニケーション力を育む、実のある教材になるはずです。
社内では、
「子どものころ、よく『人生ゲーム』というボードゲームをしました。学年を問わず、家に集まって、人生に関する出来事を疑似体験できるため、とても楽しかったです。最初は負けてばかりいた子も、何度もするうちに交渉方法を学んで、強くなっていきました。顔を突き合わせてコミュニケーションを取って遊べることが、メリットだと思うので、ぜひ現代の小学生たちにも遊んでほしいです」
「今は、通信型のゲームを持ち寄り、公園や家の玄関に集まって遊ぶ子どもを見かけます。私の子どもも熱中しています。ゲームのなかのキャラクターを使って協力し合うのですが、これも現代のコミュニケーションの形だと思います。ボードゲームなどと異なり、相手の表情や気持ちを読み取るのはなかなか難しいかもしれませんので、そればかりするのではなく、体を動かすスポーツにも取り組み、コミュニケーション力を養ってほしいと思っています」
「アナログ・コミュニケーションを、社員研修などに取り入れている会社があると聞きます。たとえば、社員をグループに分けて、協力し合ってパズルを完成させたり、オリエンテーリングをして社員同士の会話を増やしたりするのです。パソコンに向き合うことが多い社員にとっては、刺激になるようです。わが社でも季節ごとにイベントなどがあるので、今まで以上に、社員間でコミュニケーションをはかっていきたいです」
という意見が出ました。
現代では、コミュニケーションを取るのが面倒くさいと感じる人も多いようです。携帯電話、スマホのメールや会話ツールが広まったため、直接顔を合わせたり、話をしたりしなくても、会話ができるためです。しかし、直接顔を見て話すことで、相手がどのような考えを持っているのかを深く知ることができますし、相手の表情や言動が身近に感じられるため、相手の気持ちをよく読み取ることができるようになります。
このような能力を養うには、ボードゲームのほか、「鬼ごっこ」や「かくれんぼ」なども有効ではないでしょうか。アナログゲームは、製作者側から一方的に与えられるだけでなく、想像力を膨らませ、ルールや遊び方を遊び手自らが生み出せるメリットがあります。昔の子どもが遊んでいた遊びを、コミュニケーション不足解消のために取り入れてみましょう。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」