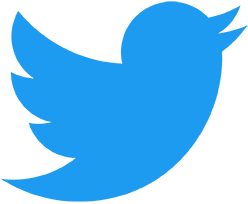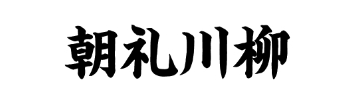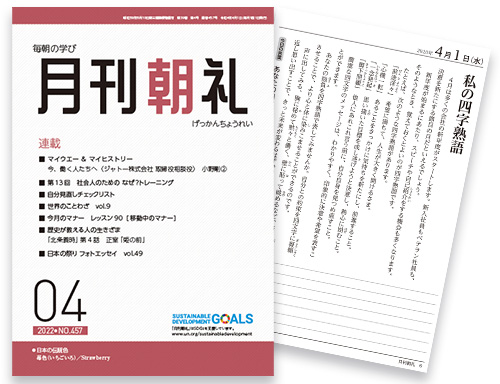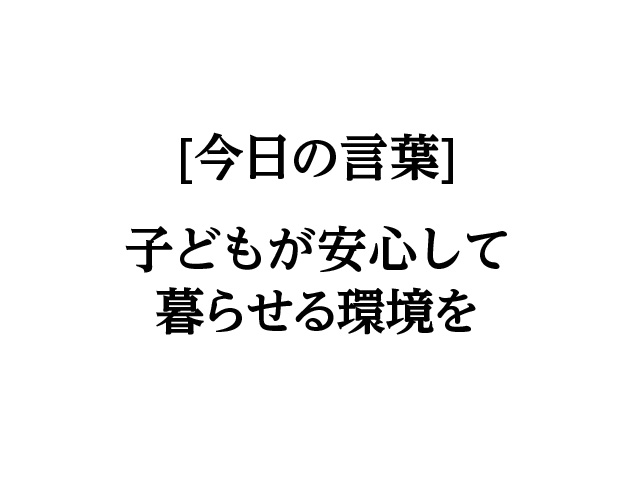
おはようございます。
電機メーカーで働く部長のSさんは、小学5年生のころに父親を事故で亡くしました。葬儀から数日後、Sさんが1人で壁にボールを当てて遊んでいると、隣の家のおじさんが、Sさんに「キャッチボールしよう」と声を掛けてくれました。うれしくて日が暮れるまで一緒にキャッチボールをしたそうです。「少年の私が寂しそうな背中をしていたのでしょうね」とSさんは言います。
その体験から、Sさんは1人で寂しそうに遊んでいる子どもを見かけると、「一緒に遊ぼうか」と声を掛けるようにしているそうです。同時にSさんは子ども会やボランティア活動に積極的に参加し、コミュニケーションをはかって、名前と顔を知ってもらうようにしています。地域ぐるみで、子どもを見守ることが大切です。
社内では、
「現代は、子どもが知らない人に連れ去られるなどの社会不安があり、なかなか子どもに声を掛けにくい世の中です。しかし、家庭や学校で孤立している子どもがいることも事実なので、それは地域で見守っていき、対応しなければいけないのではないかと思いました」
「Sさんのように、寂しそうに遊んでいる子どもに『一緒に遊ぼう』と声を掛けると、今はすぐに不振な目で見られてしまいます。ですので、地域活動に積極的に参加し、顔と名前を知ってもらう工夫は良いことだと思います。子どもも知っている人なので声を掛けやすいため、私も町内会の掃除や運動会などに参加して顔を知ってもらうつもりです」
「子どもがいますが、知らない人に声を掛けられたらついていってはいけないと指導しています。しかし町内会の絆が強く、他の家の子どもと交流を持つ機会も多いので、1人でいる子どもにも声を掛けますし、その親にも子どもが1人で遊んでいたよと言える関係ができています。そのような仕組みを他の地域にも伝えていく活動もしています」
という意見が出ました。
40年くらい前の日本ならば外で遊ぶ子どもも大勢いましたし、町内で知らない大人もあまりいませんでした。また家族が全員で食事をしたり、三世代が同居したりしていて家族の絆も強かったでしょう。しかし、今は核家族化が進み家族の絆が弱くなっています。子どもが安心して暮らせるように、地域ぐるみで子どもを見守ることがより重要です。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」