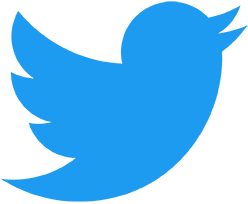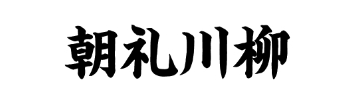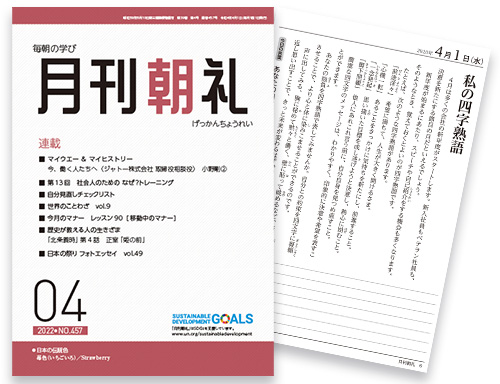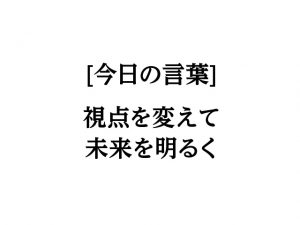
おはようございます。
「これは絶対にこうあるべきだ」「そうするべきではない」というふうに、「べき」という言葉をよく使う人がいます。「べき」という言葉は、その人の考える正しさ、つまり固定観念が基準にあり、それから外れたものを正そう、という意識から出てきます。しかし、基準の枠をはみ出した新しい考え方も受け入れる、柔軟な姿勢も必要です。
社内では、
「父が『あれをすべきだ』とよく言っていたので、学生時代までは影響を受け、友人に考え方を押しつけていました。しかし、社会人になり、多くの人の考えを知ることで、父の考えの方が古かったり一方的だったりしていたことを知りました。これからも柔軟な考え方をしていきたいです」
「規律を守る人は、一方で融通の利かない人と捉えられます。時と場合によって、良いところは受け入れ、悪いところははっきりと意見を言うことが大切です。物事に固執し過ぎないように、さまざまな見方をしていきます」
「私は『べき』という言葉をよく使います。人の話をあまり聞き入れず、視野が狭いとよく言われます。今まで以上に人の話をよく聞いて視野を広げ、選択肢を増やしていこうと思います」
という意見が出ました。
世の中にはさまざまな人がいて、多様な考え方があります。自分自身が今までに知らなかった、思ってもみなかった新しい考え方をする人も当然います。そのような人に出会ったときは、柔軟かつ謙虚な姿勢で接しましょう。そうすれば、人間関係はうまくいき、自分自身もきっと成長するはずです。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」
#月刊朝礼 #朝礼