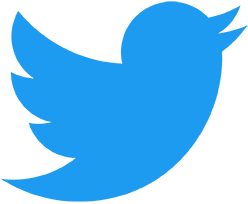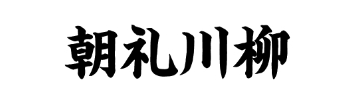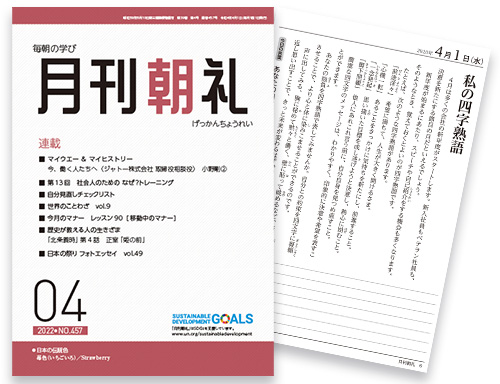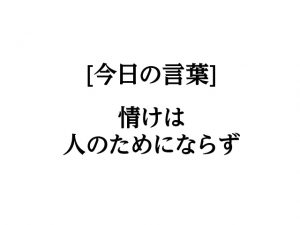
おはようございます。
1890年、トルコの軍艦エルトゥールル号が、和歌山県串本町の紀伊大島沖で沈没しました。親善航海の帰途、台風に巻き込まれたのです。地元である大島村の住民たちは、生存者たちの救護に努め、乗組員69名が救出されました。
それから95年後の1985年、イラン・イラク戦争のさなか、イランに取り残された日本人を、トルコ政府は自国民より優先して救出しました。トルコの駐イラン大使は、「トルコ人なら誰でも、エルトゥールルの遭難の際に受けた恩義を知っています」と答えました。
大島村の住人の見返りを求めない無償の行為が、時代を経てもなお、トルコ人の心に感謝の気持ちを根づかせていたのです。
社内では、
「目の前の困っている人を助けることは、その人を救うだけではなく、未来にもつながっていくのだと感動しました。個人でできることは限られていても、その思いは多くの人に届き、国さえも動かすことができるのです。私もこれからは、未来の子孫や国のためにも、率先して困っている人を助け、また恩返しをしていきたいです」
「私の出身地では、先祖の行いや人柄が、今でも人間関係に色濃く反映されます。たとえば『あなたのおじいさんにはお世話になった』『あの家のおばあさんはいい人だった』などのことで、家族ぐるみの親しい付き合いが続いていきます。都会で暮らしているとそういったつながりを意識することが少なくなりますが、自分の行いが将来にも影響することを常に忘れてはいけないと思いました」
「助けたり、助けられたりすることで、人と人の間に『縁』が生まれます。エルトゥールル号の乗組員を助けた村民たちは、日本とトルコの間に、素晴らしい縁を生み出してくれました。私もこのような縁を生み出すことができるように、人との出会いを大切にし、よい行いを心掛けたいと思います」
という意見が出ました。
今年は、日本とトルコが友好関係を築いた125周年にあたります。それを記念して両国の関係を描いた映画『海難1890』も制作されています。
エルトゥールル海難事故から始まる2つの国の恩返しの話は、現在も色褪せることなく、人々に受け継がれているのです。串本町と在日本トルコ大使館の共催による慰霊祭が、今も5年ごとに行われているのも、恩が後世に引き継がれているからです。
誰かが困っているときに手助けをするのは、人として当然の行為です。また、人から受けた恩には、心から恩義を尽くさなければいけません。私たちはそのことを忘れず、未来の人たちに素晴らしいプレゼントを残せるようにしていきましょう。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」