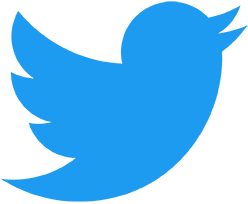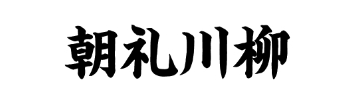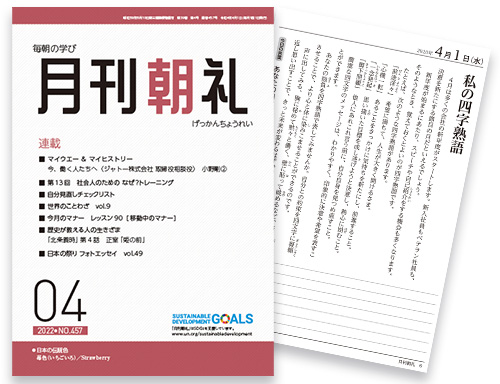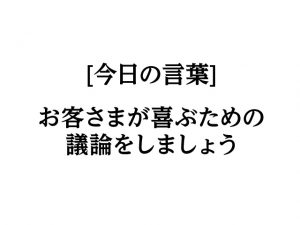
おはようございます。
LINE株式会社の元CEO森川亮さんは、「考えを率直に伝えることが重要」だと考え、社員同士に率直な発言を促したところ、けんかが起きるようになったそうです。森川さんが社内の様子を見ていると、優秀な人ほどけんかをしない、ということに気づきました。
「優秀な人も初めは腹を立てます。しかし、意見を押し通すことよりも、良いものを作りたい気持ちが大きいため、けんかをやめて議論を始めるのです」
良いものを作りたいと思っている人たちは、やがてそうではない人を相手にしなくなるのです。良いものを作るために働いているという信頼感が社員同士の根底にあると、勝ち負けではなく、有効な議論が成り立つのです。
社内では、
「議論をする場合、みんなの意見を聞きながら最善の手段を見つけようと努力する人と、かたくなに自分の意見を押し通してけんかを続ける人がいます。私は後者を反面教師にしています。自分の意見を押し通すより、お客さまが何を求めているのか、どうすればそれを満足できるのかを話し合うことが有意義だと思うからです。そのために、多くの人の意見を聞き、最善の手段を導き出せる議論をするように努めています」
「お客さまが喜ぶ答えを探すために、社員同士が本音で議論を交わすことは大切です。しかし、お客さまが喜ぶことと自分の考えていることがあたかも同じものであるかのように、自分の意見やアイデアを押し通そうとする人がいます。まずは、お客さまがそれを本当に望んでいるのかをしっかりと見極め、良いものを作るために、時に自分の意見を控えることも、有効な議論の1つだと思います」
「率直に発言してもいいと言われたとき、自分の意見を押し通す人に負けてしまい、発言できないことが多いです。これではお客さまのことを考えていないと判断されかねません。やはりお客さまが喜ぶために、自分に何ができるのかを積極的に発言し、さらに良い意見があれば取捨選択してこそ、会社の一員として役立つと思います。たとえ意見がぶつかり合ったとしても、良いものを作るという理由のためなら、最後にはきっと信頼感が生まれるはずです」
という意見が出ました。
議論か口論かの判断基準は、誰のために話し合っているかです。お客さまが喜ぶために意見を出し合うことが議論であり、自分の意見を何としても認めさせたいという自分のために言い合うことが口論です。口論は平行線のまま終わってしまい、結局、あの人はわがままで他人の意見を受け入れないという結論で終わります。しかし、議論は、お客さまが喜ぶことが主題であるため、たとえ本音による言い争いになったとしても、結局、良いものができたときに、話し合ってよかったという達成感が生まれ、それが信頼感につながります。自分のためより、お客さまのために尽くすように、有意義な議論をしていきましょう。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」