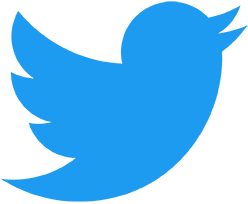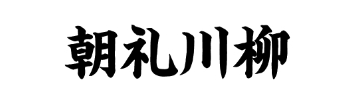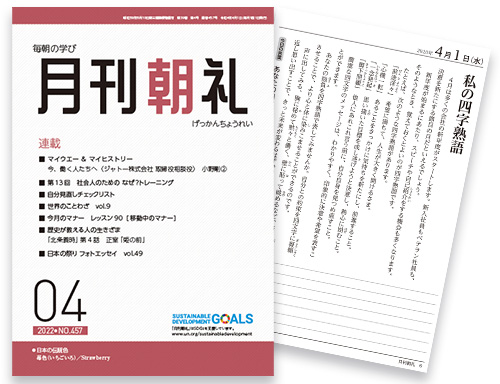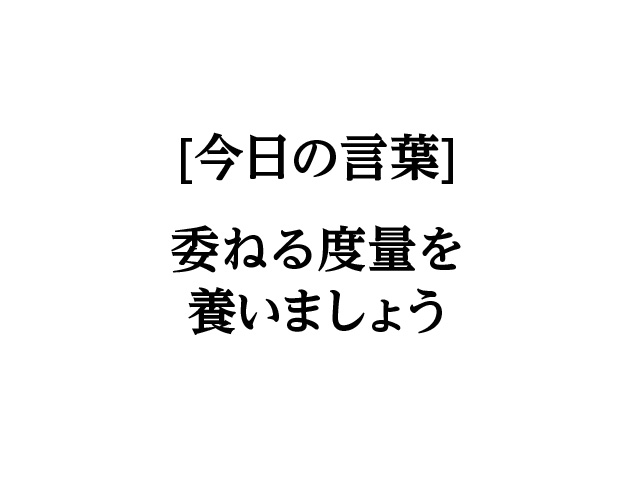
おはようございます。
江戸時代中期の老中・松平定信が、熊本藩の堀平太左衛門に幕府の行政改革について相談しました。定信が、各部門の政策の秘訣を尋ねると、堀は「各部門に聞いてください」と答えました。定信が「お前は何も知らないのではないか」と聞くと、「私の仕事は、奉行の仕事を細かく知ることではなく、彼らを気持ちよく働かせることです」と答えました。
定信は堀の言葉に、自分がいかに細かく指示を出し過ぎていたかに気づいたといいます。あなたは、部下に細かく指示を出し過ぎていませんか。
社内では、
「部下に細かく指示を出すということは、部下を信用していないからだと思います。そのような上司は、全てのことが自分の思い通りにならないと気が済まない人が多い気がします。細かく指示ばかりしていると、部下は自ら判断できない指示待ち人間になってしまいます。委ねる度量が重要だと思います」
「仕事を丸投げして、部下が何をしているのか全く分からないような人は、上司としてはふさわしくないと思います。仕事の大半は委ねながらも、ポイントをチェックし、フォローできるバランス感覚を持った上司が、良い上司なのではないでしょうか」
「各部門の政策の秘訣を尋ねられているので、堀平太左衛門は松平定信の部下として、何らかの答えを用意しておくべきだったと感じました。ある程度詳細を管理していたと思いますが、上司は管理する役割を忘れず、仕事を委ねて信頼関係を築く努力をすることが大切です」
という意見が出ました。
部下を管理する場合、重箱の隅をつつくように細かく口出しをしていませんか。そのような態度を見た部下は、自分は信頼されていないのだと感じます。部下が気持ちよく働ける職場環境を整えることは上司の重要な仕事です。そうすれば部下は任されていると感じて、意欲的に仕事をするようになるはずです。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」