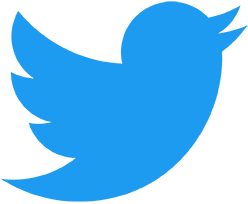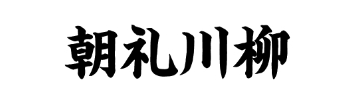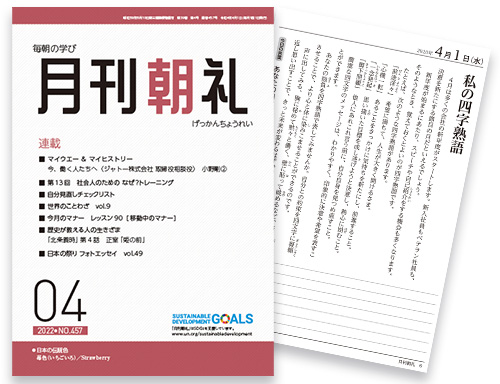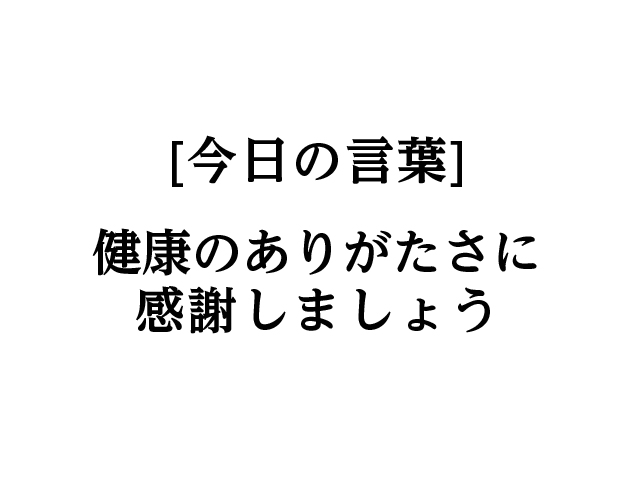
おはようございます。
七草には、ナズナの他にも、セリ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロとありますが、本日の朝礼の題名が「七草ナズナ」とされていることに「なぜだろう?」と不思議に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
人日の節句は、日本の各地で様々な習慣の中行われますが、その中のひとつに「七草囃子」というものがあります。この七草囃子も地域によって言葉は変わりますが、内容としては、日本に疫病をもたらす渡り鳥を農作物を守るために追い払う意味が込められたものだそうです。
1月7日の朝に、お粥やすまし汁など、無病息災を願う行事食として食べられる七草ですが、みなさんはお召し上がりになりましたか?
社内では、
「田舎で暮らしたこともありますが、七草ナズナというお囃子があることを知りませんでした。行事をより深く知ることで、その日の過ごし方も変わるように思います」
「昨夜、この七草ナズナを口ずさみながら、七草を刻んでお粥にして食べました。正月行事を終えて、新たな生命力を得たようです」
「今朝七草のおすましを食べました。インフルエンザなどで体調をくずす人が多い中、健康でいることを保つことがどれだけ大切で大変なことなのか思い知らされます」
という意見が出ました。
若いうちは健康が「あたりまえ」のように思えますが、年を重ねるごとに、その難しさを実感します。「あたりまえ」に健康でいられることに感謝して、規則正しい生活を心掛けましょう。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」